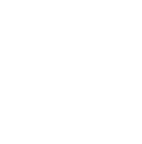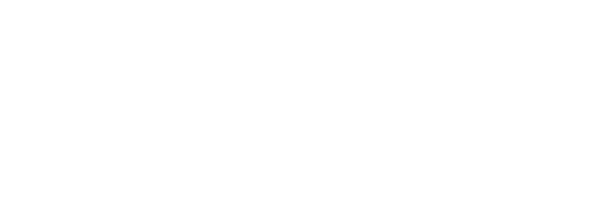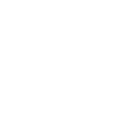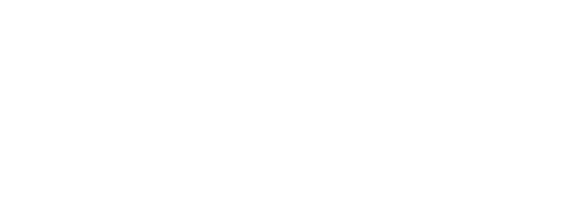新築住宅の登記費用について知りたい方必見!!登記にかかる費用や語意、実際の流れを徹底解説!
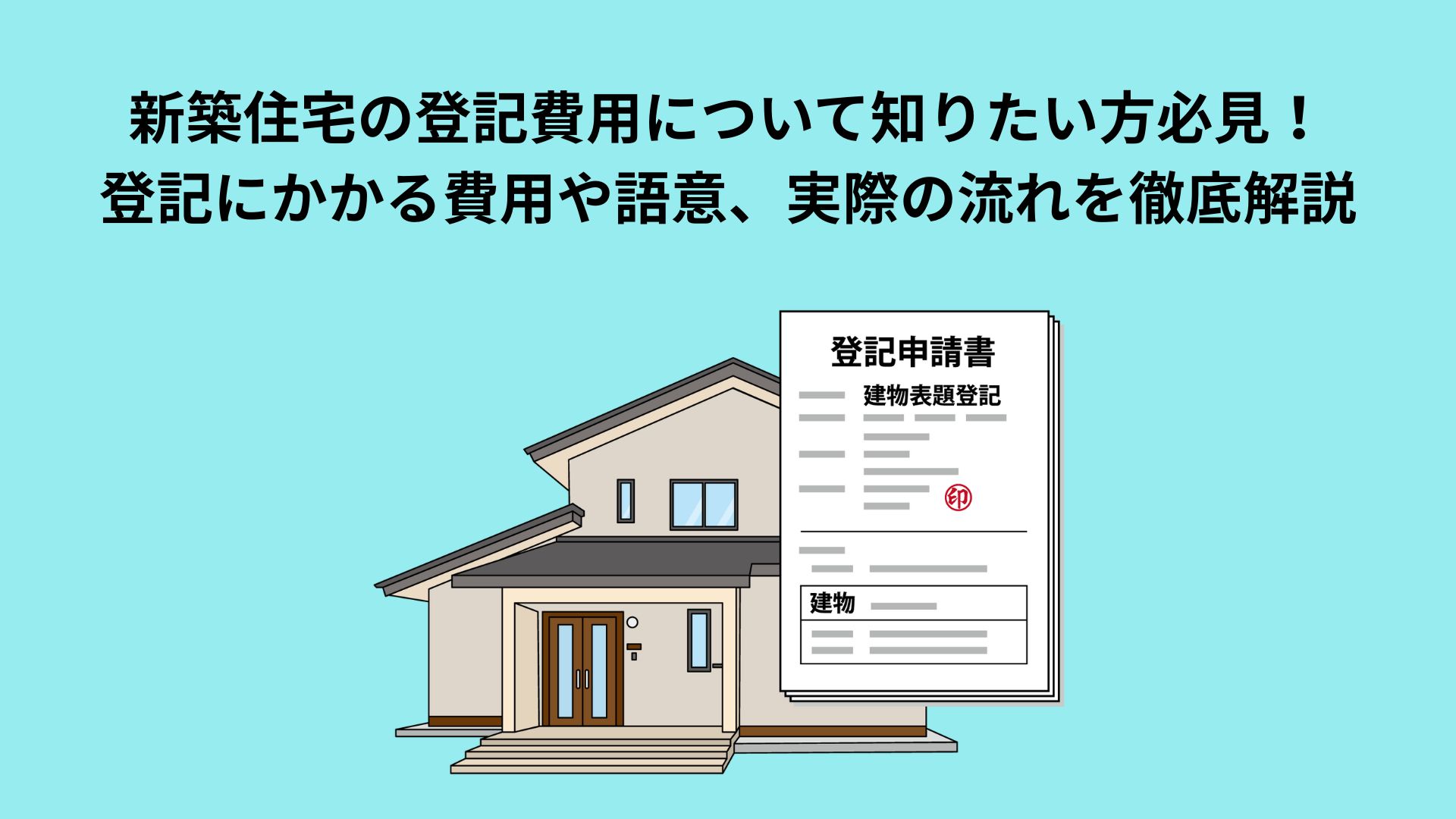
新築住宅を建築、又は購入する際に必要になってくるのが〈不動産登記〉です。「登記って聞いたことはあるけど詳しいことは知らない」「新築の登記費用ってどのくらいかかるの?」「申請の仕方がわからない」といった方も多いかと思います。
そこで今回は、新築住宅を建てた時に必要な登記の費用、申請の流れなどについて解説いたします。

登記とは
登記とは、不動産(土地や建物)などの重要な情報を、国が管理する公的な帳簿(登記簿)に登録することです。簡単に言えば「土地や建物の持ち主や権利関係を、公の帳簿に登録すること」を指します。
登記を行うことにより、誰でもその情報を確認できるようにし、取引の安全を守ることができます。
登記簿に登録された内容は、「登記簿謄本」または「登記事項証明書」という形で誰でも取得可能です。これにより、その不動産の所有者や面積、担保の有無などを確認することができます。

登記にかかる費用
登記費用の合計の目安は、25万円~50万円程度が相場となります。これらの費用は住宅購入の諸費用として、引き渡し時に支払うことになることが一般的です。
※新築戸建て、ローンを組む場合
では、25万円~50万円程度の登記費用の内訳がどのようになっているのかを見ていきましょう。
建物表題登記
土地家屋調査士への費用
建物の測量や法務局への申請書類の作成、手続きの代行で相場は8万円~15万円程度になるでしょう。
国に納める税金や手数料
印紙代、住民票などの証明書の取得費用などで、数千円程度の費用が必要です。
所有権保存登記
司法書士への費用
法務局への申請書類の作成、手続きの代行で相場は5万円~10万円程度になるでしょう。
国に納める税金や手数料
通常は建物の固定資産税評価額をもとに計算されますが、新築の場合は新築建物課税標準価格認定基準に基づいて計算されます。目安としては数万円~10万円程度になるでしょう。
抵当権設定登記
司法書士への費用
法務局への申請書類の作成、手続きの代行で5万円~10万円程度になるでしょう。
国に納める税金や手数料
借入額に応じて税額が決まります。借入額2,000万円の場合で2万円程度です。

前述したように、登記費用と一口に言っても様々な費用項目が存在しています。
家を建てる際にかかる建物や土地の費用の他にも、このような費用がかかることを覚えておくと良いでしょう。事前に費用総額を確認しておくと安心です。
登記はなぜ必要?
ここまで、登記の意味や費用について説明してきましたが、そもそも何故登記は必要なのでしょうか?本項では、登記の必要性について解説いたします。
所有者を公に示すため
土地や建物の所有権は、目に見えない権利です。登記をすることで「この土地はAさんのもの」といった情報を公的に証明し、誰にでもわかるようにします。
これによって他人が勝手に「この土地は私のものだ」と主張するのを防ぐことができます。
取引の安全を守るため
土地や建物を売却したり、担保にしたりする際、買い手や銀行は登記を確認することで「本当にこの人が所有者なのか」「他に借金などの担保になっていないか」といった情報を正確に把握できます。登記がないと安心して不動産取引をおこなうことができません。
権利関係を明確にするため
登記簿には所有権のほかに、抵当権、賃借権、地上権など、その不動産に設定されたあらゆる権利が登録されます。これらの情報が公開されることで、利害関係や権利の内容を正確に確認できます。
※抵当権・・・住宅ローンなどでお金を借りた際に、不動産を担保として設定する権利。
※賃借権・・・家や土地、マンションなどを借りた人が、それを一定期間使用・収益することができる権利
※地上権・・・他人の土地を借りて、その土地の上に建物や工作物、または竹木を所有するために、土地を占有・使用することができる権利。
登記の種類
新築戸建てを建てた際に行う登記は、大きく分けて2つの種類があります。住宅ローンを組むかどうかによって、手続きの順番や内容が少し変わります。
建物表題登記
これは、新しく建てた建物の物理的な情報を公的なものとして登録するための登記です。建物が完成したら最初に行う、すべての新築戸建てに必要な手続きで、建物が完成したら1ケ月以内に申請する義務があります。
申請者は施主本人ですが、専門家である【土地家屋調査士】に依頼するのが一般的です。調査士が建物を測量し、必要な書類を作成して法務局に申請します。
所有権保存登記
これは、建物の所有者が誰であるかを明確に記録するための登記です。これにより、その建物の所有権を第三者に対して主張できるようになります。
法的な義務はありませんが、この登記をしないと建物の売買や住宅ローンを組むことができません。そのため、事実上ほぼ必須の手続きとなります。
申請者は施主本人ですが、こちらも専門家である【司法書士】に依頼するのが一般的です。住宅ローンを組む場合は、銀行や工務店から指定された司法書士が手続きを代行してくれます。
抵当権設定登記
これは、住宅ローンを借りた金融機関が、万が一の場合に備えて、その建物を担保にしているという事実を登記簿に記録するための登記です。
これがなければ金融機関はローンを融資してくれません。
こちらも専門家である【司法書士】に依頼するのが一般的です。
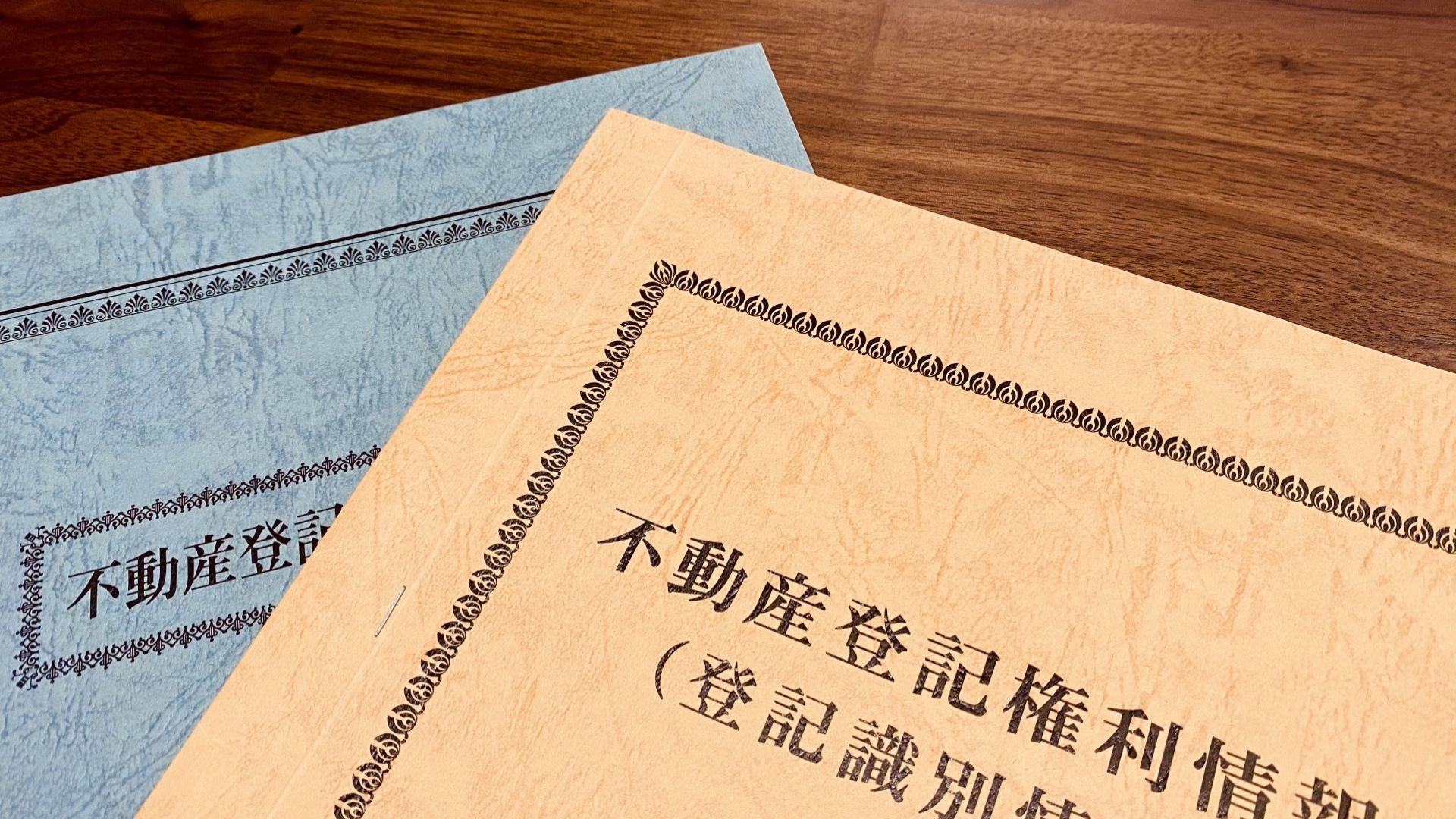
難しいと感じられがちな内容ですが、新築の引き渡し時にはこれらの手続きがスムーズに行われるように、工務店、金融機関、司法書士、土地家屋調査士、そして買主(お施主様)が連携して進めていきます。
一般的にはハウスメーカーや工務店の担当者が連携している専門家を紹介してくれるため、あまり不安になることはありません。
疑問点などは工務店の担当者に聞くと良いでしょう。
住宅ローンを組む場合の登記
もしあなたが自己資金だけで新築住宅を建てる場合は、金融機関からお金を借りないため、抵当権設定登記を行う必要はありません。ただしその場合でも、建物表題登記と所有権保存登記は、新築の所有者として行わなければならない手続きです。
ただし、多くの方が新築を建てる際に住宅ローンを組むため、ほとんどの場合は下記3つの登記が必要になってきます。
〇建物表題登記
〇所有権保存登記
〇抵当権設定登記
通常は、建物の引き渡し時に、土地家屋調査士と司法書士が連携して必要書類を確認し、この3つの登記をスムーズに完了させます。登記が完了することであなたが建物の正式な所有者となり、金融機関の抵当権が設定され、融資が実行されるという一連の流れが一般的です。
まとめ
もしあなたが新築を建てる予定であれば、工事請負契約の段階で、これらの登記手続きをどの専門家に依頼するか、費用はどのくらいかかるかなどを、ハウスメーカーや工務店の担当者に確認しておくと安心です。
新築を建てるとき、建物や土地にかかる費用の他にも様々な費用が発生します。「本体価格以外にかかる費用」についても見積もりを出してもらうと良いでしょう。